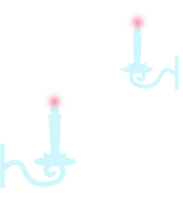ライターとして
この本を書き始めたのは、NPO法人血液情報広場・つばさの代表、橋本明子さんの厳しい一言があったからです。夫を亡くしてから、誤診について、病院と話し合いを進めていた私は、精神的に不安定でした。長年連れ添った夫を亡くし、自分だけが被害者という意識がどっかりと腰を下ろしていたのです。そのせいでしょうか。私は病院を相手に訴訟を起こそうとも考え始めていました。
そんなとき橋本さんは、「残念ながら、ご主人の病気の生存率は、厳しいものがあります。私は電話相談を通して、何千例も見てきました。裁判を起こしても、難しい結果になるでしょう。それよりも、あなたにはほかにやらなければならないことがあるでしょう。ライターとして、書かなければいけないことがあるのではないですか」。
橋本さんの、私を親身になって気遣うアドバイスに、やっと私は目が覚めました。夫の闘病記を書かなくては、と奮い立ったのです。闘病記のことは、夫が発病してからずっと書こうとは心に決めていました。ライターとして記録に残さなければと思ってはいました。
しかし、私は書くことから逃げていたのです。あの苦しい闘病生活を思い出すだけで、身体の震えは止まりませんでした。事実、原稿を書き進むほど、身体をもがれるような痛みにさいなまれました。でも、ここで止めてしまったら、女がすたる。腕力で組み伏せるように書き上げた原稿は、惨たんたるものでした。
そんな原稿を丹念にチェックしてくれたのが、編集者の藤田正明さんでした。「当時のことをもっと冷静に見つめてほしい」。藤田さんの指摘にカチンときましたが、それでも読み直してみると、事実関係はあやふや。自分の気持ちだけをぶちまけているというお粗末なものでした。よくも藤田さんは、辛抱強く付き合ってくれたと思います。妹の磯見史子もそれは同じです。何度も原稿を読み返し、「あのとき、お姉ちゃん、こうだったじゃない」とアドバイスをくれました。
こうした人々の協力もあり作業を進めていくうちに、私は、私なりに三年間の闘病生活を少しは冷静に見つめることができました。 病院の誠意も、そして病院が置かれている医学界の現状も少しは理解することができました。私はようやく、夫の死を受け入れることができたように思っています。
中日新聞社出版開発局の鈴木鉄局長にも、いくどもアドバイスをいただきました。そのほか、高校時代の友人の稲吉益味さん、大学時代の友人、北村恵子さんにも頭が下がるばかりです。職場で机を並べているスタッフも、よくもまあわがままな私に付き合ってくれていると、感謝の念に耐えません。 私は温かい多くの人々に囲まれて、今を生きています。夫もまた、同じだったに違いありません。これから、私にどんなお返しができるのでしょうか。いろいろ考えましたがその一つとして、運動に共感したNPO法人血液情報広場・つばさで、電話相談を始めることにしました。何が私にできるのか。まるで自信はないが、とりあえず一歩ずつ、歩いていこうと思っています。
(あとがきより)